 2023.05.29
2023.05.29 147
147

「新卒でもテレワークで仕事がしたい」
「どんな業種を選べばテレワークができる?」
など、就活においてテレワークを視野に入れた進路を考えている人も多いはず。
コロナ禍以降、世の中の働き方は大きく変わりつつあり、テレワークの導入が一気に進んでいます。
ただし、全ての業界・職種で可能かといえば難しく、必然的に現場に出て業務が必要な業種も存在します。
もしテレワークを希望している就活生であれば、選択する業界・職種によってはテレワークと相性が悪い可能性もあるでしょう。
今回は就活準備中の人に向けて、テレワークができる職種の条件や避けるべき業種について解説します。
構造を理解しておけば、少しでもあなたが希望する進路に近づくはずなので最後までご覧ください。

テレワークはどんな仕事でも可能になるわけではありません。
一定の条件を満たしている必要があるため、まずはテレワークに必要な条件について確認していきましょう。
テレワークでは遠隔の状態で、社内の連絡やお客様とのやりとりができる業務内容であることが必須です。
遠隔であればオンライン上でやり取りするため、対面でコミュニケーションが必要な業務の職種はテレワークに向いていません。
例えば、店舗販売はテレワークとは完全に相性が悪い職種です。
他にも下記の職種はテレワークが難しい職種といえます。
テレワークでは場所と時間に制限されないことは大前提となります。
どんな場所でも業務に差が出ず、影響も受けない職種でなければなりません。
パソコンとネット環境で、ほとんどの業務が完了できる必要があるので、もっとも相性が良い職種は「情報通信業」といえるでしょう。
テレワークは企業側から従業員の実態が見えづらい環境になります。
業務をしている姿を確認できないため、適正な評価をするためにも明確な成果物を残せる業務であることも必要です。
代表的なのが事務職で、形になって見れば達成度を分かるため評価もしやすいといえます。
出社していれば明確な成果物が無くても、日頃の頑張りや過程が見えるものの、テレワークになってしまうと結果のみで判断する形になります。
したがって、やるべき業務がハッキリと決まっている事務職のような職種はテレワークに向いているでしょう。
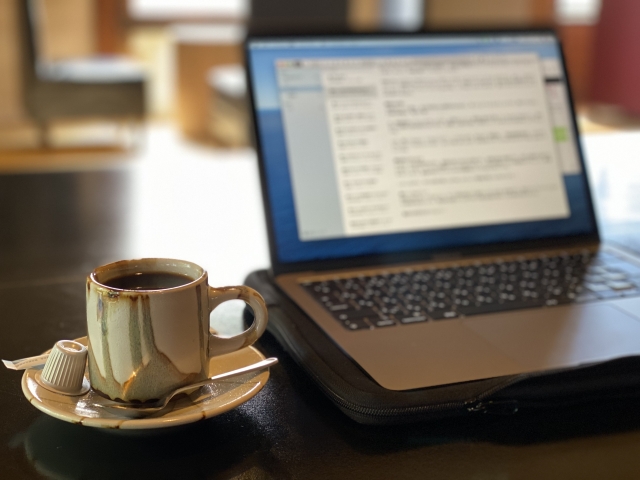
近年は働き方改革も進むと同時に、コロナウィルスによってテレワークを進める企業が一気に増えました。
多くの企業が導入を進めていますが、実際どの業種がテレワークの実施が進んでいるのでしょうか。
テレワークの導入が最も進んでいる業種はIT系です。
同じ業種内で見ても、約半数以上はテレワークの導入に成功しているデータもあります。
やはり、パソコンがあれば成り立ってしまうIT系は必然的に導入が進んでいますね。
テレワークで仕事をしたい就活生であれば、IT系を目指しておけば間違いはありません。
その次は金融、通信・インフラが続いてテレワークの導入が進んでいるようです。
業種によって、テレワークの実施率は大きく変化します。
よって、業種選びに失敗すれば必然とテレワークからは遠ざかることになるので注意しましょう。
小売・飲食では一部の層を除いて、テレワークの導入は進んでいません。
本部でパソコン作業をしている従業員であれば、テレワークが考えられるかもしれませんが、店舗や現場にて立ち会いが必要となるポジションの従業員は導入が難しいでしょう。
どうしてもその場で対応が必要となる業務が多い業種だけに、今後もテレワークの導入は難しい形です。
AIやロボットの進化で働き方は自然と変化する可能性がありますが、小売や飲食のような現場に人が必要となる業種でテレワークの導入はなかなか難しいのが現実でしょう。

ここからはテレワークができない職種の紹介と理由について解説していきます。
テレワークができる仕事を目指す就活生であれば、これから紹介する職種は避けておきましょう。
先ほど紹介した小売・飲食業や宿泊業などが接客業に含まれます。
接客業は対人で成り立つ職種になるため、現場で業務に従事することは必須です。
接客業のなかでもバックオフィス部門になればテレワークの可能性も考えれます。
しかし、新卒で入社した場合は経験を積むためにも現場からスタートする可能性が高いため、最初からテレワークになるケースは稀でしょう。
最近は技術の進化により、ロボットやITによって接客自体を人間がしない動きもありますが、接客以外の部分で現場作業が必要になるので、テレワークは難しいと考えたほうが賢明です。
介護や福祉関連は、利用者のサポートを直接的に行う必要があるのでテレワークがほぼ不可能になる職業です。
こちらも介助におけるロボットなどの進化が期待されていますが、人間でしかケできないアやサポートの部分も多くあるため、テレワークは難しい職種になります。
公務員は情報のセキュリティ面によってテレワークが難しい職種になります。
市役所などの役所勤務であればテレワークできるのではと考える人も多いでしょう。
ただし、住民の個人情報を大量に扱っているので、情報漏洩の危険性もあり、職場以外の情報持ち出しは厳禁になっています。
したがって、役所務めでもテレワークは難しいと考えておきましょう。
警察官や消防員に関しても、現場で業務に従事することが基本業務になるため、テレワークでは成り立たない職種です。
建設業にも種類はありますが、ほとんどが現場で作業する業務になるのでテレワークは成り立たない職種となります。
現場に出ない部門になったとしても、建築業界自体でテレワークを導入しているケースが少ないので、出社して業務に従事するスタイルになるでしょう。
製造業は技術進化したロボットが多く、自動化が年々進行しています。
しかし、ロボットが仕上げた製品をチェック、生産管理の必要性から人間の力がまだまだ必要です。
製造業の現場における業務内容は変化していますが、テレワークに移行するのは難しいと考えておきましょう。

年々、新卒でもテレワークで業務を行う職種の求人は増えつつあります。
企業側もテレワークで教育を進めるノウハウを持っているため、しっかりと教育を受けながらテレワークに従事することは可能でしょう。
とはいえ、就活生は社会人スキルのない未経験者でもあるため、中途採用者と比較してしまうとテレワークの求人数は少ない形です。
なんとしてもテレワークができる求人を見つけたい場合は、求人サイトやハローワークを使って「テレワーク 新卒」「フルリモート 新卒」など、関連するキーワードで徹底的に企業を探し出しましょう。
大手企業だけに絞らず、中小企業やベンチャー企業まで幅広く視野を広げてください。
近年はベンチャーで斬新な理念や考えを持っている企業が増えているため、新しい働き方であるテレワークもベンチャーで多く採用されている印象があります。
ぜひチェックしてみてください。
テレワークに必要な条件やテレワークができない職種について解説しました。
年々、テレワークによる働き方は注目され、企業も導入を進めている様子が伺えます。
ただし、新卒でテレワークを希望する場合は導入が進んでいる業種をターゲットにして就活を進める必要があるでしょう。
自分の適性や目指すゴールと照らし合わせたうえで、テレワークできる職種を選ぶようにしてください。
仮に、すぐにテレワークができなかったとしても、一定の知識やスキルを身につけた後にテレワークに移行する企業や異動によってテレワークができるようになるなど、入社してから狙えるケースもあります。
企業研究をするなかで、将来的にテレワークへ移行できるかも含めてリサーチかけるようにしてください。
